PROGRAM
巻き込み型リーダーシップ研修
タコツボ化した中堅社員の
働くエネルギーを高める4つの駆動力
Outlineプログラム概要
- 対 象 者
- ・30-40代中堅社員選抜型次世代リーダー
マネジャー手前のリーダー層 - 推奨日数
- ・2日(9:00-17:00)
- 受講者数
- ・1クラス24名まで(最小10名~最大36名程度)
Before/Afterビフォーアフター

対象者中堅社員(特に5~7年目)
- 自分の仕事をまわすのに精いつばいで周囲(上司・部下・他部署・顧客)に関われない
- 自分がどうなりたい、どんな仕事がしたいのか将来像を描くことができていない
- 問題点を頭ではわかっているが、主体的に問題解決ができていない
- チームの目標にコミットする立場としての自覚に乏しく、自分の仕事に引きこもり、その領域から出ようとしない


自身とチームのありたい姿、周囲の巻き込み、
現場での実践方法を体得
- ー担当者としての業務にとどまっていたものが、視座が高くなることで業務レベルが向上
- 上司を補佐し、部下を指導するといった、周囲を巻き込むための行動がとれるようになる
- 自分のキャリアと組織での役割・期待がリンクすることで主体性を身につけることができる
BasicConcept基本構想
巻き込み型リーダーシップのイメージ
次世代リーダーとしての意識・行動をすり込む設計
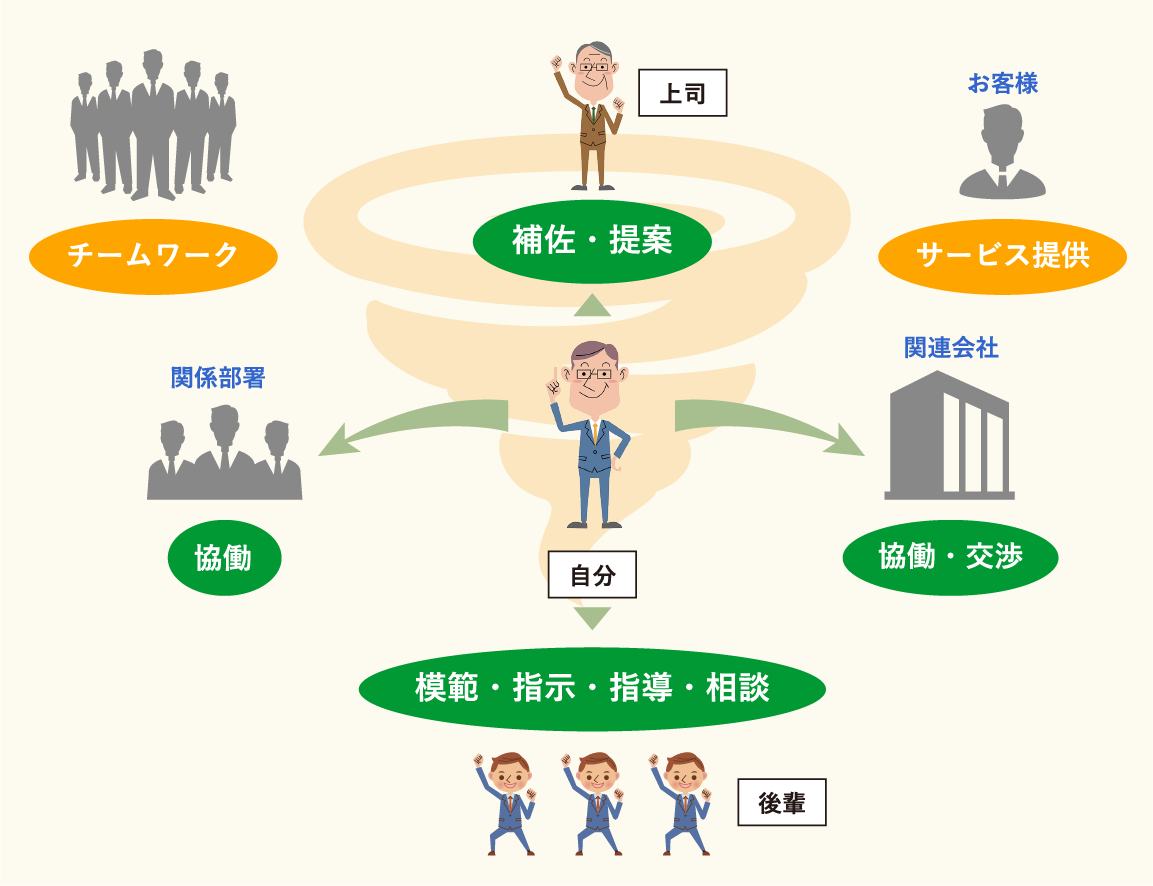
- 問題解決を図る際に、今までより巻き込む範囲を拡大し、根本的な問題解決を図ることができる
- より高い視点と広い視野で物事を捉え、組繊業績の成果や中長期視点を持ち、組織の中心メンバーとして貢献する
- 担当業務外についても周囲から相談を受ける機会が多い
- 自分の成果より組織の成果や下位者の成長への関心が高い
- チーム全体
-
- リーダーを中心に周囲が機能している
- 協働と共育の文化が根付いている
- 周囲
-
- お互いに学び合う
- 目標達成に邁進する
- 不満は提案に変える
巻き込み型リーダーシップに必要な能力
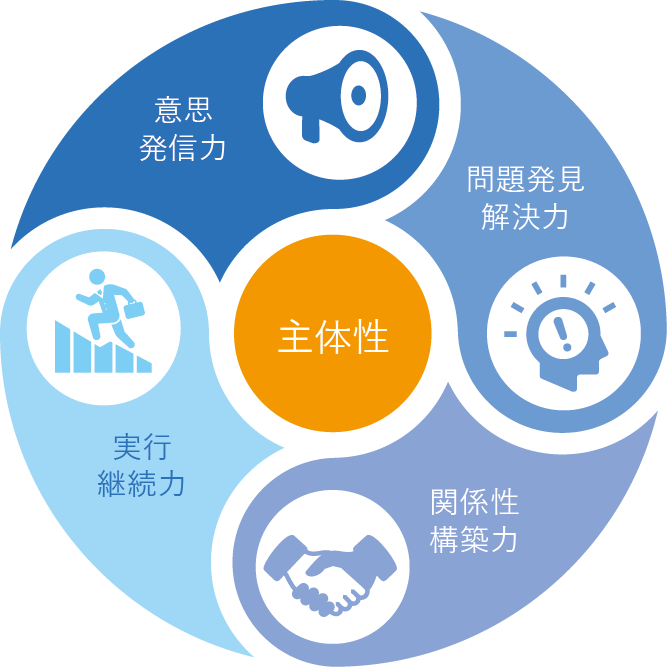
巻き込み型のリーダーに必要な能力として、「主体性」というコアと現場で実践するために必要な4つの駆動力(ドライバー)を学びます。
巻き込み型リーダーシップを発揮するためには視点を高め視野を広げ、時間軸を長く持つ思考の拡充と、組織の範囲を超えた他者への働きかけの拡充が重要です。
- 主体性
- リーダーシップの根源を探る
- 意思発信力
- 自身なりの目的・使命を語る
- 問題発見・解決力
- 視野拡大・視点移動をして問題を捉える
- 関係性構築力
- 周囲への働きかけを学ぶ
- 実行継続力
- ポジティブに考える
Feature研修プログラムの3つの特徴
1過去と現在の自分を見つめ直し、自身の思考の特徴を把握する
ビジネスゲームYes! Boss! で自分自身の思考のクセを知り、現状の確認と過去の経験を振り返る。
今までのキャリアを見つめ直し、自分の今後の理想のキャリアを想い描く。
2周囲を巻き込んで取り組むことの重要性を考えさせる
「主体性」というコアと、現湯で実践するために必要な4つのドライバーを学習する。
「意思発信力」目的・使命を語る、目的を打ち出す
「企画構想力」問題を捉える、問題解決ストーリーを描く
「関係構築力」共感し合う関係になる、上司を補佐・提言する、後輩の模範になる・指導する
「実行継続力」メンタルタフネスを高める、ポジテイブに考える
3学習に沿って自チームヘの応用を言語化させる
現場実践手法で巻き込み型リーダーに必要な知識を身につける。
経験学習サイクルを職場で回すための方法を習得する。
4つのステッブについて、今後チームで取り組むこと、部門で取り粗むことを内省・実践シートに落とし込み、職場で実践するきっかけを与える。

Contentsプログラム内容
巻き込み型リーダーシップの理解
イントロダクション
私たちの現状
- 現状の確認と過去の挑戦【グループワーク】
- 今の状態と心理的要因【個人ワーク】【グループワーク】
- Yes! Boss! 【演習】【振り返りワーク】
私たちへの期待
- 周囲を巻き込んで取り組むことの重要性・考え方
- コアと4つの駆動力
- 【意思発信力】
- 目的・使命を語る/目標を打ち出す
- 【企画構想力】
- 問題を捉える/問題解決ストーリーを描く
- 【関係構築力】
- 共感し合う関係になる/上司を補佐・提言する/後輩の模範になる・指導する
- 【実行継続力】
- メンタルタフネスを高める/ポジテイプに考える
目標設定シートの作成・実践サポートシート
- 演習:リーダー自身が藉る
- 演習:ビデオケース「星野リゾート」
- 演習:参画をデザインする
ポイント③:協働
- セルフフィードバックレター作成・行動宣言
研修のまとめ
Voice受講者の声
「人を動かす」ということの具体的な実践方法が学べた。
今後、メンバーが参画し、協働していくような強いチームとすべく、自ら思いを伝えていきたい。
何事も単独での成果よりチームとして協働したほうが、より大きな成果が得られると確信した。
